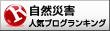7年前にTOCANAで私が執筆した記事を再掲するが、大地震や大水害には、約400年の周期があることが、国立の「総合地球環境学研究所(地球研)」の科学者の研究で判明したという重要な内容となる。
■TOCANA記事
この記事は、7年前の2017/10/08にTOCANAに掲載されたものの概要となる。
TOCANAでは既に削除されている。
記事は、『【衝撃】「大地震・洪水の連鎖が400年周期で起きる」国の調査で判明! 現在ガチでサイクル突入中、3つの危険地帯はどこ?』と題したもの。
国立の「総合地球環境学研究所(地球研)」の研究で、大地震や大水害には、約400年の周期があることが判明した。
400年前といえば、ちょうど慶長地震の大地震シリーズがあった頃で、非常に興味深い研究なので紹介することにした。
総合地球環境学研究所(地球研)の中塚武教授らが、樹齢数千年の古木を調査したところ、気候変動には400年の周期性が存在することがわかった。
■400年周期
中塚武氏は、400年程度の周期で変動する 「小氷期」の存在を提唱した。
地球の気候変動における太陽活動の関連性について研究されている、日本の著名な気候学者だ。
400年前の前回は、ちょうど慶長地震など一連の大災害シリーズがあった時期と重なる。
現在は400年に1度の水害危機の時期に入ったと考えられ、今後さらなる大地震・大水害の発生が懸念される。
400年前の1600年頃から1700年代初めにかけては、著しい洪水が頻繁に発生していた。
慶長三陸地震は、1611年12月2日に発生したM 8~M9クラスの巨大地震と考えられている。
奇しくも、ちょうど400年後に同じ三陸沖で、東北地方太平洋沖地震(M9.1)が発生した。
この400年サイクル説がもっと早く注目されていれば、三陸沖の巨大地震に対して防災観念を高めておくことができただろう。
■400年前の周期
以下に、TOCANAの記事で執筆した地震・洪水リストに、月齢との関係がわかるように追記した。
【-2】1586/01/18 22:00頃:天正地震(飛騨・美濃・近江)、M7.8~M8.1、犠牲者多数
【新】1586/01/20 03:05:
【満】1590/03/21 14:02
【0】1590/03/21:安房。
【-3】1596/09/04:慶長豊後地震(別府湾口)、M7.0、犠牲者708人
【-2】1596/09/05:慶長伏見地震(京都市伏見区)、M7.5、最大震度6相当、津波、犠牲者1000人以上
【満】1596/09/07 01:42
【-5】1597/10/06:白頭山噴火
【新】1597/10/11:
【-1】1605/02/03:慶長地震(南海トラフ説)、M7.9〜8、津波10m位(諸説)、犠牲者約5千人
【満】1605/02/04 07:17:
【新】1609/01/06 11:16
【-5】1609/07/12:甘粛、酒泉地震、M7.3、犠牲者840人。
【月】1609/07/17 08:25:皆既月食
【満】1611/09/22 11:38
【+5】1611/09/27 09時頃:会津地震、M6.9、犠牲者3700人余。
【-2】1611/12/02:慶長三陸地震、M8.1、犠牲者約2千~5千人
【日】1611/12/04 08:03:金環日食
【新】1615/06/26 11:18
【0】【南関東】1615/06/26:慶長江戸地震、M6.2~6.7、死傷者多数
【-2】1616/09/09:宮城県沖地震、M7.0、三陸地方で大津波。
【月】1616/09/11 10:44:金環月食
【+5】1616/09/16:チリ・アリカ地震、M7.5
【満】1619/04/29 02:01
【+2】1619/05/01:肥後(熊本)八代、M6.0、旧八代城が倒壊、竹田城(大分県)が破損。
【新】1620/06/01 05:17
【+2】1620/06/03:阿蘇山噴火
【+5】1620/06/06:ミャンマー中部・マンダレー、M不明
■それ以前の周期
このように、特に慶長年間(1596~1615)の間は大地震や大洪水が相次いだ時代だった。
そのために文禄から改元されたのが1596年であり、慶長になっても災害連鎖は止まないため、1615年に元和と改元された。
「慶長大地震」というのは、慶長年間に起こった一連の地震災害の総称となる。
単に「慶長地震」と呼ぶ場合は、1605年2月3日に起きたM 7.9〜8の大地震を指す。
この地震は、南海地震(南海トラフ)、南海沖・房総沖の連動など、震源や規模に関しても諸説ある。
上記の400年サイクルよりも古い大災害となると、大地震は断片的に記録されているだけで、また水害の記録はほとんど残っていない。
以下に、そのごく一部を記しておく。
【1600年前頃】
・416年8月22日:允恭地震、奈良県明日香村。規模不明。
【1200年前頃】
・818年8月頃:弘仁地震、M 7.9、北関東。犠牲者多数。
【800年前頃】
・1200年頃:地質調査によると南海トラフ地震が発生した可能性がある。
・1202年5月20日: レバノン・シリア・イスラエル、M 7.7、犠牲者数千人。
こうなると、前述の400年前の災害データで、慶長豊後地震(大分)、慶長三陸地震(三陸沖)、熊本(熊本地震)は、すでに対応する地震が起きたと解釈できる。
それ以外の大地震などに警戒が必要だろう。
具体的にいうと、中央構造線断層帯、近畿地方、そして南海トラフで起こる巨大地震となる。
以前から何度も書いているように、東日本大震災の影響による地震・噴火の連鎖は終わったわけではない。
私が用いる「大災害シリーズ」は、10年・20年単位で繰り返されるが、3.11頃から始まった周期は、まだ続いている。
その意味でも、今後の数十年間は、大地震・火山噴火・大水害に悩まされることを覚悟して、防災に励まなければならないだろう。
●8
【Amazon】『防災グッズ セット リュック 1人用 非常用リュック』
※こういう写真を使いたくなるほど強烈な耳鳴りが朝から続いている。