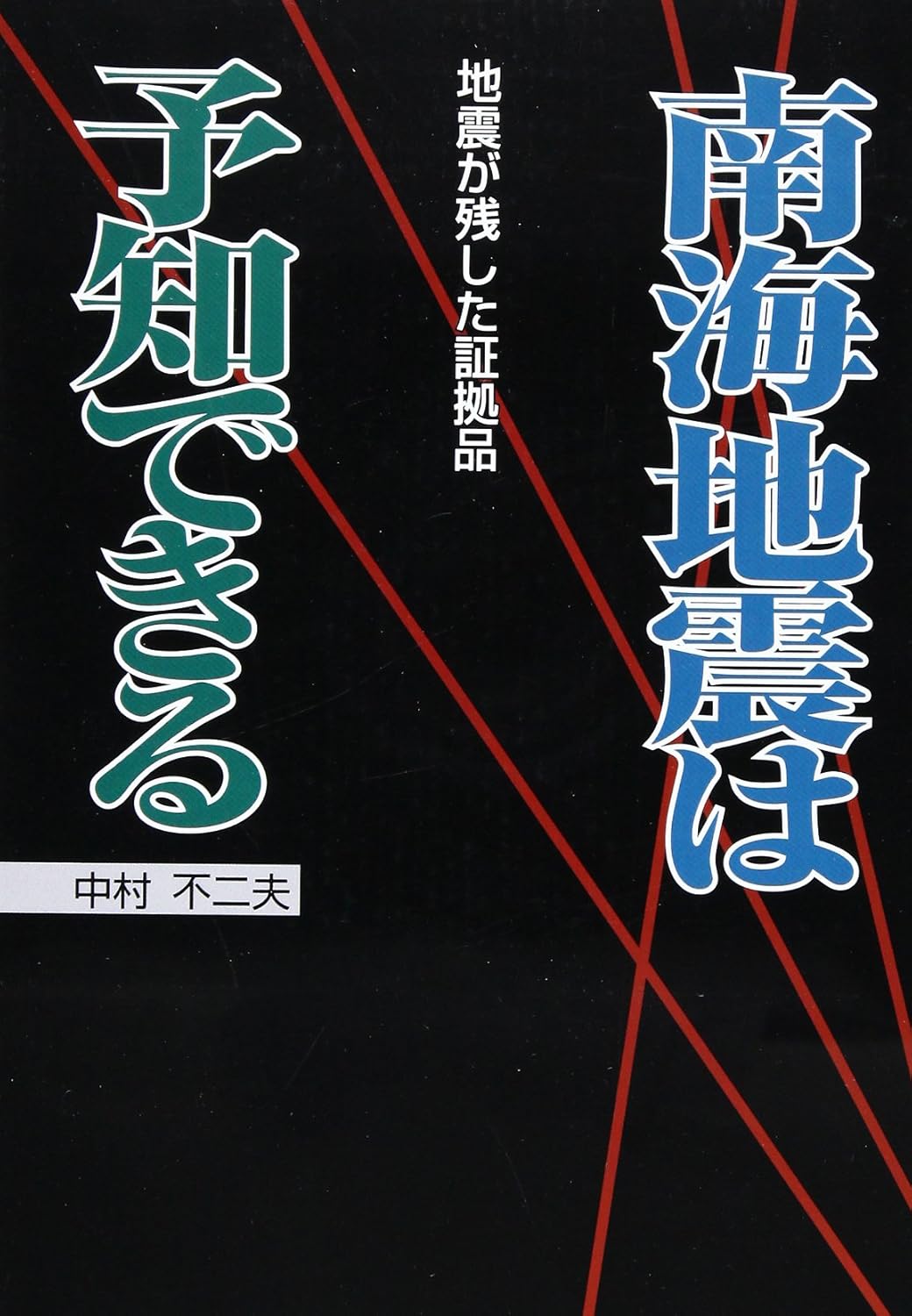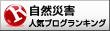今日09/26に、政府の地震調査委員会は、南海トラフ地震の発生確率について発生確率の算出法を見直したと発表して、2つの確率を併記するという異例の事態となったが、自分の研究と比較して検討したい。
■南海トラフ確率
今日09/26に、政府の地震調査委員会は、南海トラフ地震の発生確率について、発生確率の算出法を見直し発表した。
今年1月の時点では、発生確率を30年以内に「80%程度」としてきた。
それが今回は複数の計算方法を採用し、新たな数値を公表した。
それによると、今後は「60~90%程度以上」または「20~50%」と併記する。
ニュース報道によると、関係者がわかりづらいと語り、不評のようだ。
※朝日新聞(後半は有料)
他の大地震の確率計算に比べ、このモデルを使う南海トラフのみ高い確率値が出るとして、「水増しではないか」との批判が昨年の国会で取り上げられた。
そもそも、大地震の発生確率は、どの程度信用できるのか。
過去に25年間ソフトウエア設計開発を行ってきた自分にとって、ある事象を確率論だけで考えることは無理がある。
このような不確かなことをメインにして、いつ大地震が起きるかを予測することには賛成できない。
■独自の予測基準
南海トラフ巨大地震の発生時期については、長期的な基準としては、下記の3つのものがある。
(1)発生時期の法則性
(2)黒潮流路
(3)エルニーニョ現象
(1)発生時期の法則性
過去の南海トラフ巨大地震はすべて7月~2月に起きていた。
次回も、この期間に起きる可能性が高いと思われる。
(2)黒潮流路
自説では黒潮の直進期(非大蛇行期)に発生の可能性が高くなる。
今年4月に黒潮大蛇行が終息して、現在は発生の可能性が高まったと考えている。
(3)エルニーニョ現象
過去の南海トラフ巨大地震の発生時にエルニーニョ/ラニーニャ現象のどちらが多く起きていたかというと、どちらでもない「平常期」に最も多く発生していた。
ただし、平常期とエルニーニョ期の発生回数に大きな違いはなく、場合によってはエルニーニョ期に起きる可能性も考慮しておくべきだろう。
そうなると、現在は(1)~(3)の条件のすべてが揃っていることになる。
このため、政府の検討方法とは全く別の観点から、南海トラフ巨大地震は「いつ起きても不思議ではない」という考えに同意することになる。
以上は長期的な観点からになるが、より中期・短期的予測としては、『南海地震は予知できる』著者の中村不二夫氏の優れた研究がある。