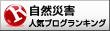今日10/28は国内最大規模であるM8.0の濃尾地震が起きてから134年経ったが、この地震の発生タイミングを調べると、「新月」と「遠地点」の2つのトリガーあったようだ。
■濃尾地震
濃尾地震は、明治24年(1891年)10月28日に、現在の岐阜県本巣市を震源として発生した内陸直下地震だった。
1891/10/28 06:38:濃尾地震、M8.0、犠牲者7,273人、負傷者17,175人
ちょうど日の出の前後に起きたようで、大地震としては良くあるパターンだ。
日本の内陸地震としては観測史上最大規模だった。
この地震によって、7,273人が亡くなった。
これは、1885年以降で知られている大地震のうちで4番目に多い数だった。
ちなみに、その上位には、1位から大正関東地震(1923)、東北地方太平洋沖地震(2011)、明治三陸地震(1896)がある。
■月齢データ
この地震の発生時の月齢は、以下の通りだった。
本震の3日前には、前震と思われる地震が起きていた。
【-8】1891/10/25 21:14:前震、M6.0
【-5】1891/10/28 06:38:濃尾地震、M8.0、最大震度7相当
【遠】1891/10/29 13:56:遠地点
【新】1891/11/02 03:31:
まず、新月の5日前の「新月トリガー」の地震だった。
また、上記のように遠地点の1日前で、「遠地点トリガー」の地震でもあった。
近地点というのは、月が地球に最接近するタイミングで、これと満月・新月が重なればスーパームーンとなる。
遠地点の方は、近地点の逆で、月が地球から最遠の位置に来る時のこと。
これと満月・新月が重なるとマイクロムーンと呼ばれる。
■遠地点も重要
通常、私自身も含めて、遠地点は月が最遠となるために地震の影響は与えないだろうと考えていた。
だが、「月の遠近カレンダー」を購入してから、作者に影響を受けた。
このカレンダーでは、近地点・遠地点・スーパー/マイクロムーンといった重要なポイントを記している。
Amazonで2026年版を探したが、まだ発売前のようだ。
調べていくうち、過去の大きな地震は、遠地点の近くでも起きていたものがあることがわかってきた。
濃尾地震も、その一つだった。
ちなみに、このあたりのことは、私が作成して公開している有料noteのデータ集『大地震・火山噴火と満月・新月・スーパームーン・日食・月食の関係』で、データを付している。
たとえば古いところでは、1648/06/13の相模・江戸の地震(M7.0程度)が、遠地点の1日前に起きていた。
■天体配置
次に、発生時の天体配置を見ると、巨大地震として特に顕著なアスペクトはできていない。
Tスクエアが見られる程度だった。
だが、8つの天体が60度以内くらいに集まった惑星集合ができていた。
これは大地震の発生タイミングとして、顕著なものだろう。
これに加えて、今ならば様々な宏観異常現象や、私が行なっているような様々な形での地震予測手法で、ネット上で騒ぎになっていたかもしれない。
■今日の地震前兆
今日は、朝8:30頃に2階の寝室の7インチTVで、4チャンネルで画像乱れが起きていた。
また、今日11:30に右耳で耳圧と共に数秒間、いつもよりも強い耳の閉塞があり、その後に金属音の耳鳴りが続いた。
天体配置的には明日あたりまでが特に要注意で、その後は11/05のスーパームーントリガーに入るため、世界的にM6クラスの地震が頻発しているが、今後も続くだろう。